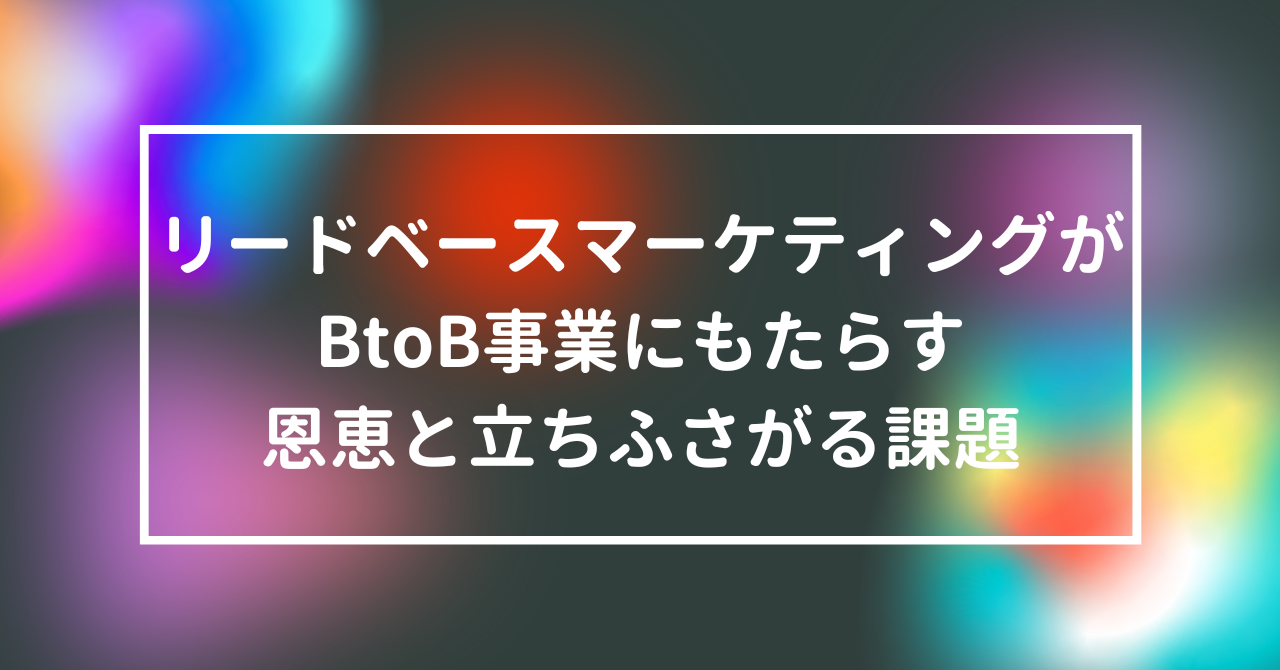
リードをとって商談をつくって、受注をとる。いわゆるリードベースのマーケティングを採用しているBtoB企業は多い。
この記事は、私のBtoBSaaSマーケターとしての実体験をもとに、リードベースマーケティングを採用した際の、恩恵といずれぶつかるであろう壁(課題)についてまとめたものです。
たくさんリード(見込み客)をとって、たくさん商談をつくって、たくさん受注する。
これがBtoBビジネスにおけるリードベースマーケティングの基本的な考え方だ。
リードベースマーケティングは、定置網漁に例えるとイメージしやすい。定置網漁では、魚がいそうな場所にあらかじめ網を設置しておき、多くの魚を大量に獲得する。引き上げた網の中には、様々な大きさ・種類の魚がいる。
リードベースマーケティングも同様に、とにかく大量にリード(魚)を獲得することを優先する。そのため、あらゆる場所(チャネル)に網を設置するというのが基本戦術となる。
リードをとるための手法(チャネル)としては、展示会、WEB広告、セミナー、ホワイトペーパーなどがある。
例えば、お役立ち資料やセミナーなどのコンテンツを自社のWEBサイトに用意して、フォーム通過させることで個人情報を取得したり、展示会に出展して、そこで大量の参加者リストを得るという施策である。
例えばこんな感じのマーケティングプロセスがあげられる。

これらの手法は、ある種、教科書化されているため、それを組織に正しくインストールできれば、わかりやすくリードは増えて、商談も増える。
BtoBSaaS界隈では、リードベースマーケティングは、もはや常識になっており、ほとんどの企業で採用されています。(そもそもの対象顧客が数十社しかないといったような、よほどのニッチビジネスをしていない限りは。)
リードベースマーケティングを行うと、結果として、リードや商談が大量に増えます。
また、それにともなって最初は売上も伸びるでしょう。この結果には、経営陣も現場も歓喜するでしょう。
しかしながら、そのままずっと順調に売上が伸び続けるかというとそう単純な話ではない。どこかで必ず伸び悩みます。
具体的には、商談化率・受注率が悪化して、営業効率が悪くなります。当たり前ですが、大量のリードや商談の中には、どれだけ育成しようが顧客になりえないデータが入ってきます。
このことに向き合わずに、リード・商談をとにかく獲るというメッセージを出し続けると、リード獲得チームは、変なリードを取り始め、インサイドセールスチームも絶対に決まらないアポイントを取り、フィールドセールスチームは、毎日商談に追われるが、受注はしないという状態になります。
こうなる前に、リードベースマーケティング、一辺倒の考え方から脱却する必要がありあす。
商談化率・受注率が悪化を改善し、効率的に売上を伸ばすためには何をすれば良いでしょうか?
根本的な解決策は、自社の顧客となり得る企業を明確にして、その顧客のリードや商談のみを集中して獲得する方向に精錬させていくことです。要は、ターゲットを絞るということです。いわゆる、アカウントベースドマーケティング(ABM)というやつです。
極論ですが、確実に決まる商談が目標受注数分、担保されれば事業としては良いわけです。
ここで勘違いしてはいけないのは、リードベースマーケティングがまったくダメと行っているわけではないです。
リードや商談を創出することは引き続き重要です。
リードベースマーケティングの思想だと、無駄なリードや商談も取る方向に力が働きやすいという性質があるので、ターゲティングの考え方も取り入れることで無駄なリードに力を注がないようにコントロールするのが必要です。
また、ABMの話をすると、アウトバウンド施策とイコールでとらえている方も多いですが、セミナーやホワイトペーパー、展示会といったようなインバウンド施策も行います。このようにアプローチ手法(チャネル)という点は、リードベースマーケティングと変わりません。
変わるのは、コンテンツをターゲットに最適化していくという点です。例えば、セミナー、一つにしろ、万人受けする汎用的なノウハウを伝える内容にして参加者を多く集めるのではなく、参加者が少なくなってもいいので、業界特化型のセミナーにするなどのアクションが考えられます。
重要なのは、「リード数を集めることよりも、商談化率・受注率を改善し、受注数を高めること。」です。
そのためには、まずターゲットを絞るというのが重要です。当たり前のことのように聞こえますが、意外とこの問題は、はまっている人も多く、また実際にうまくやるのは結構難しかったりするので気を付けたいところです。